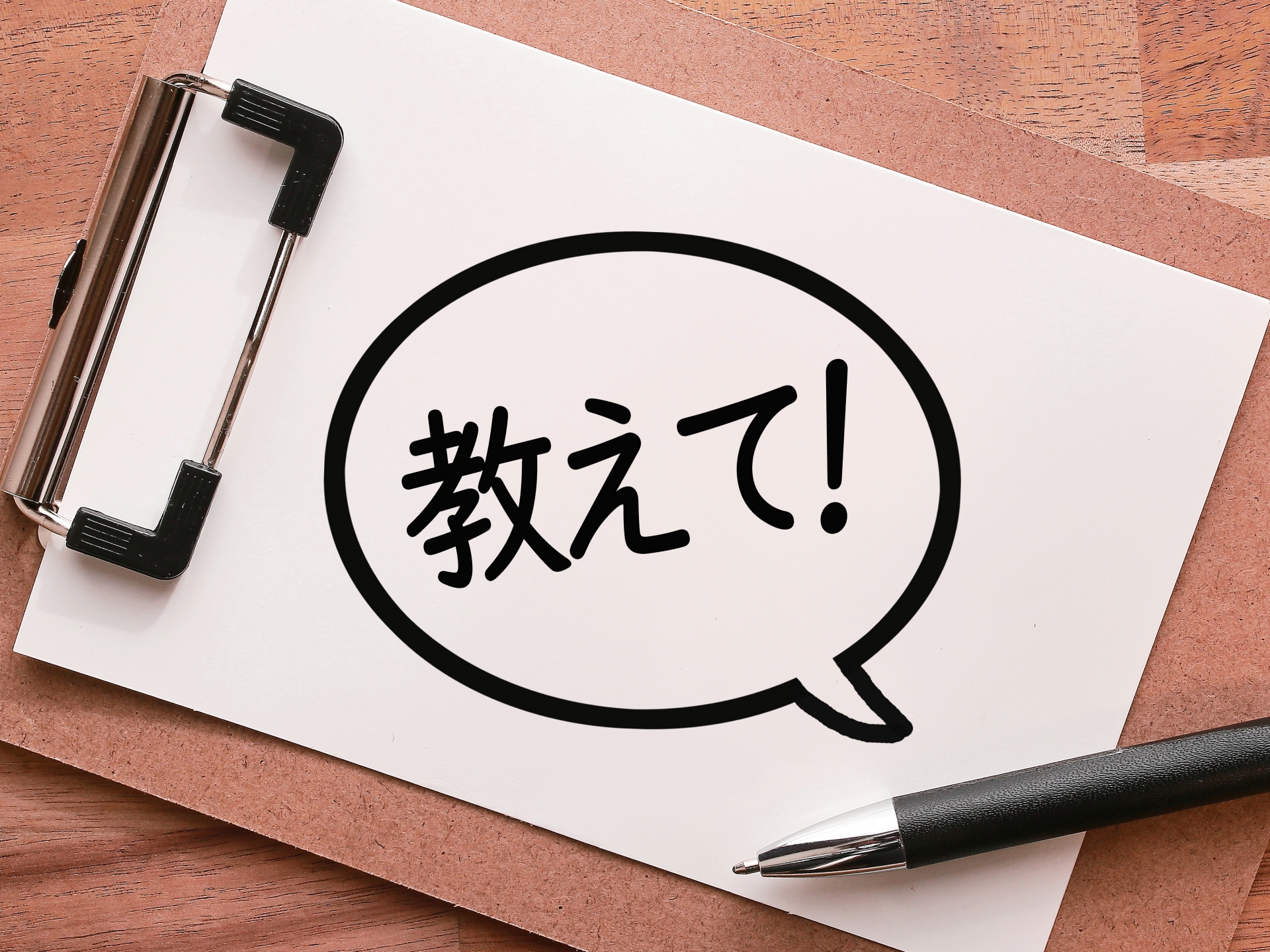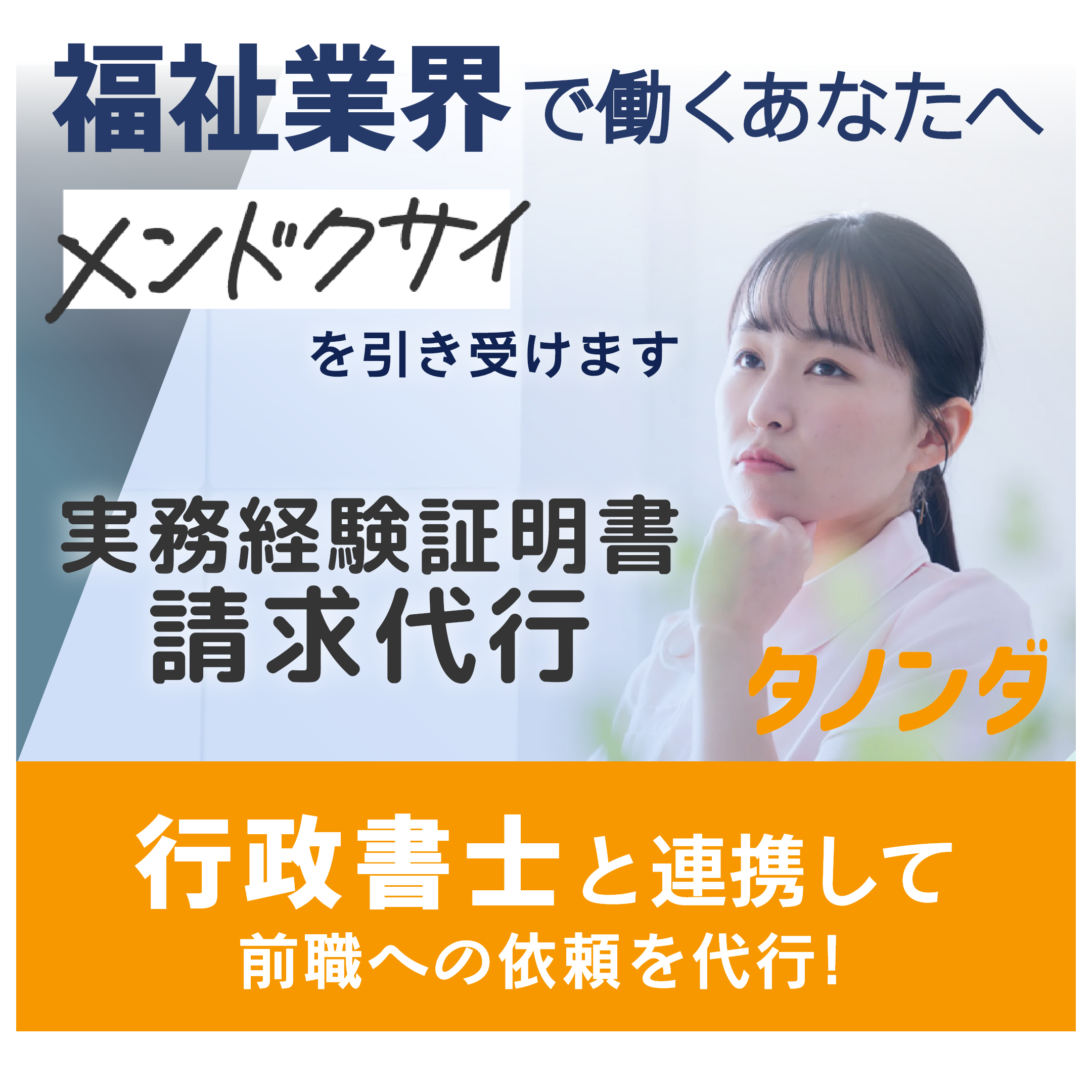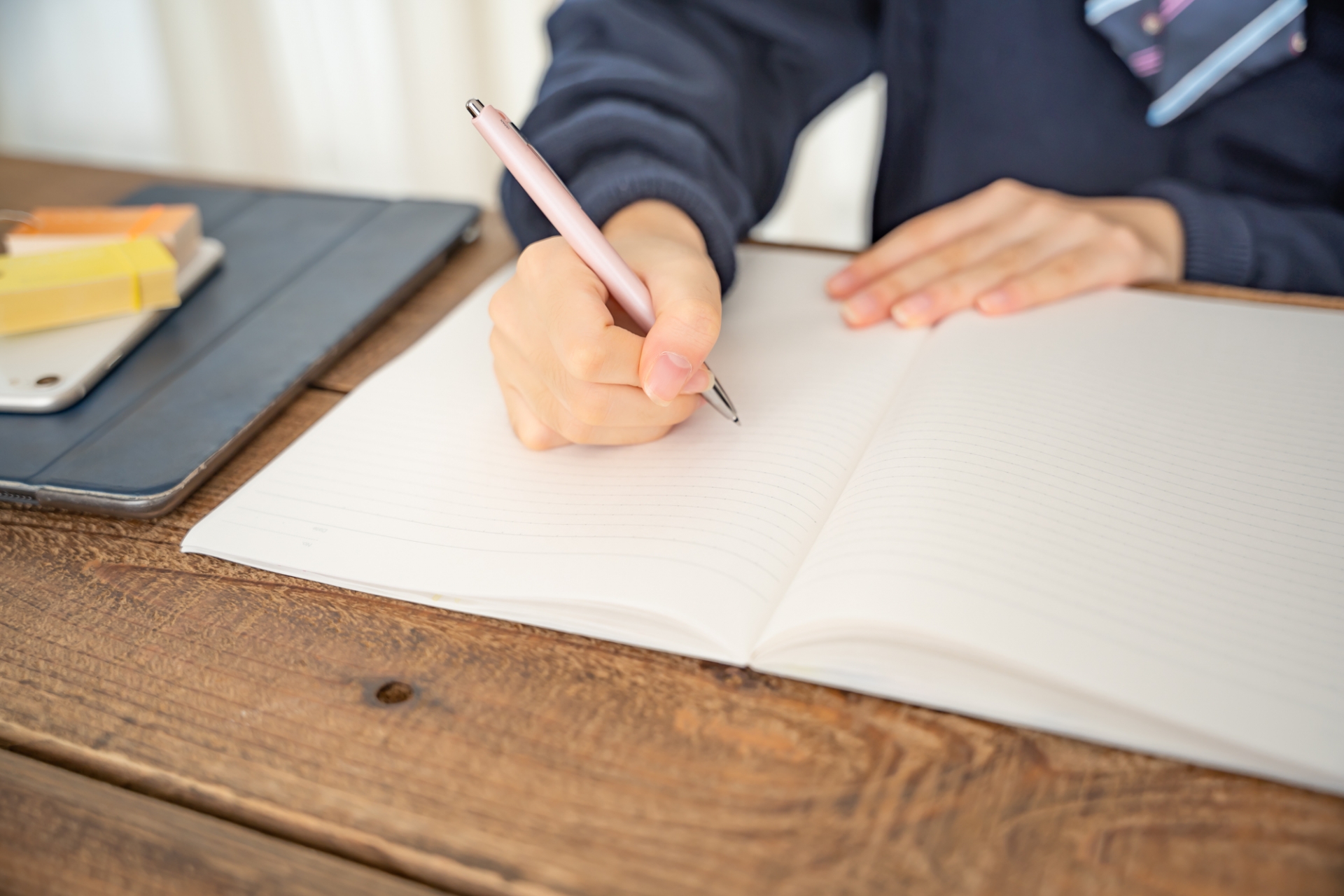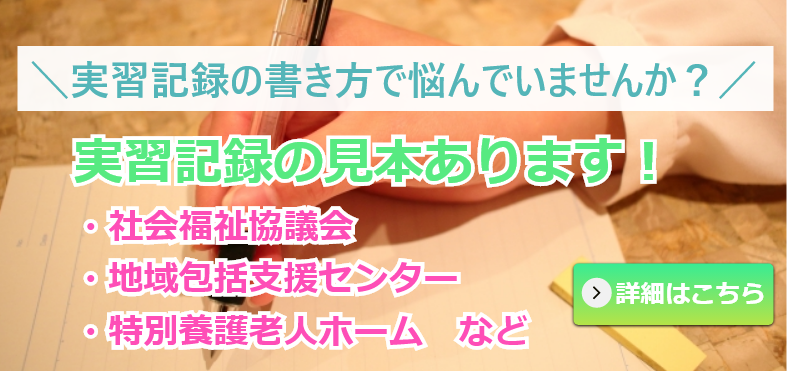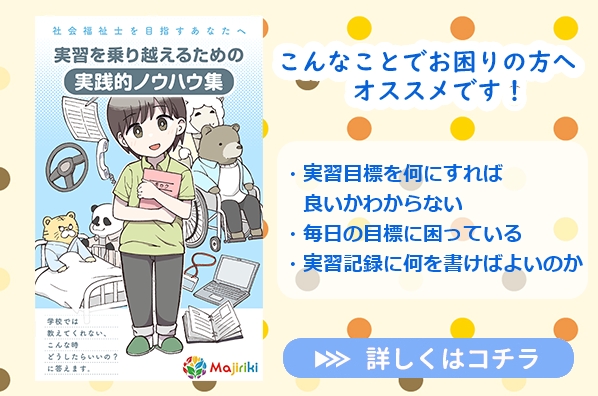この記事では、障害者福祉の理念を概観した後、障害者支援において重視すべき点を述べ、その上で、「自分らしい生活」の実現について考察する。考え方の一例として参考にしてください。
障害者福祉の理念
障害者福祉の理念であるが、国連は1971年に知的障害者の権利宣言の採択、1975年にはすべての障害者が対象となる障害者の権利宣言を採択し、ノーマライゼーションの理念は掲げられた。さらに、1981年の国際障害者年では、完全参加と平等という世界的な理念を持ち目標へ向けた実践が目指された。2006年には障害者の権利に関する条約を採択、各国が条約締結に向かうこととなった。我が国も条約批准のために総合支援法や障害者差別解消法等が整備され、2014年に批准した。これにより完全参加と平等の理念のもと、差別をなくし、合理的配慮を行うことで参加を促し、共に生きる社会の実現が目指されている。
日本での障害者に関する法律は先に述べた世界の動向に大きな影響を受けている。基本とする法律に障害者基本法があり、個人的人権の尊重がなされながら共生社会の実現のため、障害者の自立と社会参加の支援等の基本事項が定められている。どのような障害があろうとも、その人自体に価値があり、障害の有無に関わらず等しい社会生活を送る権利を持つことを保障されていることを忘れてはならない。
現代では、さまざまな障害がありながらも普通の生活ができる社会環境をつくるノーマライゼーションの考えが広まっている。また、障害の捉え方は、ICFの登場と障害者権利条約の考え方をもとに大きく変わり、「障害」は「心身機能障害」と「社会的障壁」との相互作用により日常生活と社会生活に相当な制限を受ける状態と変更された。
これらを踏まえて障害者支援において重要すべきは、「自分らしい生活」を実現することを目標として、その過程で本人の人権尊重として自己選択や自己決定がなされていること、身体機能だけでなく、環境因子、個人因子などが影響して社会参加を妨げていないか全体俯瞰的に把握することであると考える。
「自分らしい生活」の実現や自立支援
「自分らしい生活」の実現や自立支援については、本人を尊重した自己選択や自己決定が重要であるが、その過程については支援者がしっかりと介入しなければ、単に自己選択や自己決定を本人に任せるだけでは求める理想に至ることはできないと考える。
これまでの経験の中で、重度心身障害者の地域生活支援を行った際、本人の希望としては地域で一人暮らしをしたいという意向を持っていた。
しかし、本人の描いている理想の一人暮らしは、現在の施設を出て自由な生活することを楽観的に考えており、そこに至るまでに何をすべきなのか、一人暮らしを始めた後に何を自分でしなければならないかということが具体的に想定できていなかった。
筆者は一人暮らしをするという選択を尊重し、何が必要なのかを現実的に本人とすり合わせることにした。
理想として考えている一人暮らしと現実の何もかも自分で行わなければならない一人暮らしにおいて、必要なことを洗い出し、これからすべきこととしっかりと向き合ってもらった。障害者の一人暮らしを受け入れてもらえるような住宅を探したり、地域で生活する際の支援者や事業所との契約、一人暮らしを始めた際の金銭管理の方法など多岐に渡っていた。
その中で種々の選択肢を提示することで、本人の中で理想と現実の折り合いをつけながら、時には自分自身で新たな方法を考えながら自分が納得できる選択をしていくことができた。事業者間や社会資源活用の調整には支援者が入り、環境上の障壁を乗り越えるようにした。勿論、調整事すべてを支援者側で行うのではなく、本人自身の力を見極めながら、エンパワメントすることで、サービスが利用できない時間に入ってもらうボランティアとの時間調整や地域の方とのコミュニケーションの取り方など着々と一人暮らしに向けた力をつけることができた。
ここまで見たように「自分らしい生活」の実現や自立支援を具体的に考えたときに必ず社会的な障壁は存在しており、それらには立ち向かわなければならない。本人の自己選択や自己決定だけではそれらの障壁を乗り越えることが出来ず、それらを乗り越えるために支援者が存在している。あくまで障壁を乗り越えるのは本人であり、支援者は本人が持つ能力を見出し、発揮できるように支援するエンパワメントアプローチの視点や、本人自身の持つ強み、本人が地域環境から社会資源を活用するストレングス視点が重要である。
生活は連続性があり、一時点で完結するものではない。生活は良いことばかりではなく、辛いことや苦しいことも存在しており、支援者も24時間ずっとついていることはできず、それらに対処する能力も身につけていかなければならないため、本人の能力を高めることは不可欠である。
支援者は本人が「自分らしい生活」の実現できるよう自己選択・自己決定を尊重しつつ、環境・社会に依存する障壁の解消に努め、その他社会的障壁には本人が対応できるよう伴走しエンパワメントしていくことが重要であると考える。
参考文献
- 福祉臨床シリーズ編集委員会編(2019)『障害者に対する支援と障害者自立支援制度 第4版』弘文堂
- 社会福祉士養成講座編集委員会編(2019)『障害者に対する支援と障害者自立支援制度 第6版』中央法規
- 障がいをお持ちのお子さまを育てる保護者の方々をサポートする情報ポータルサイト 「Learning Camino」
学校では教えてくれない詳細まで記載しています!