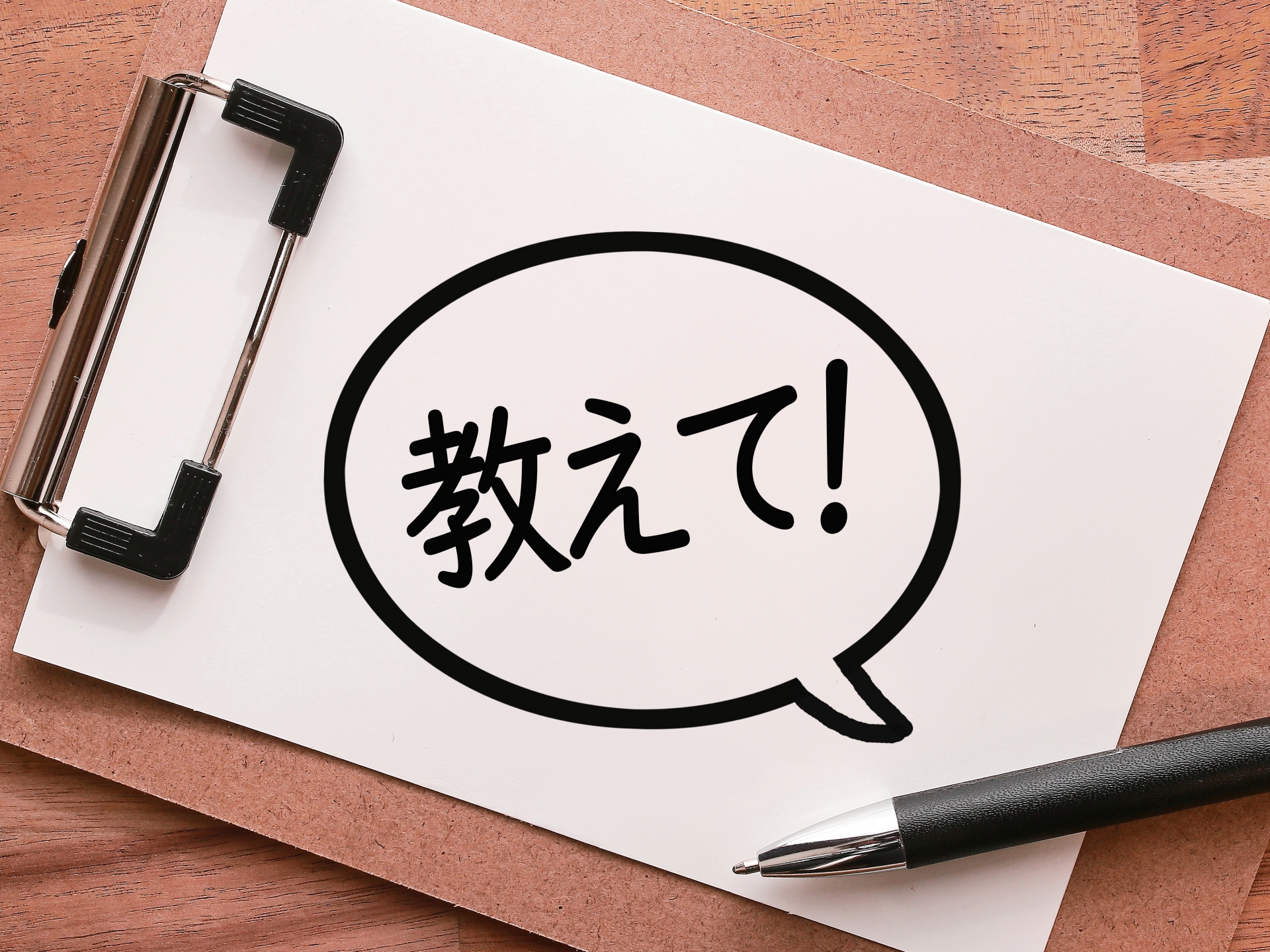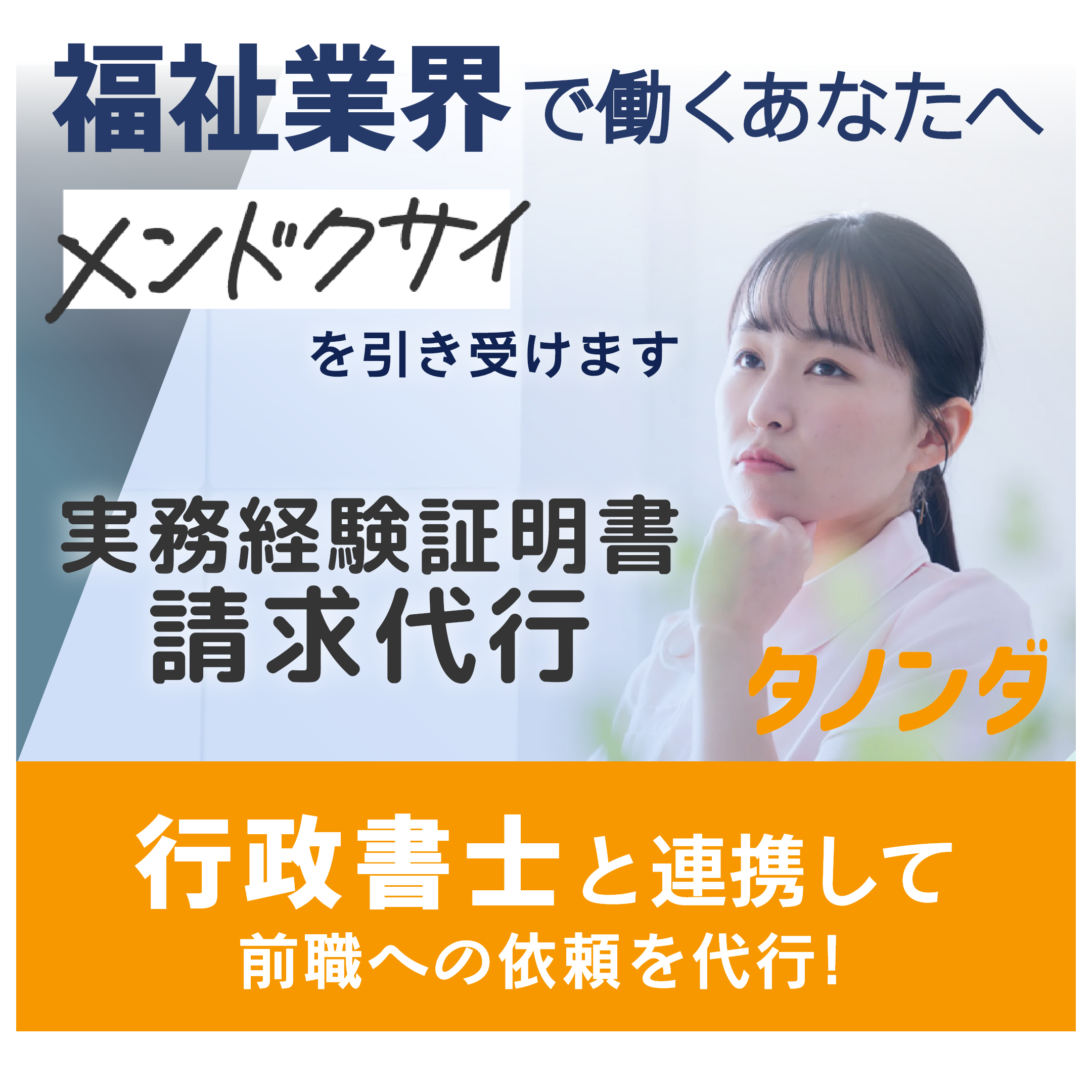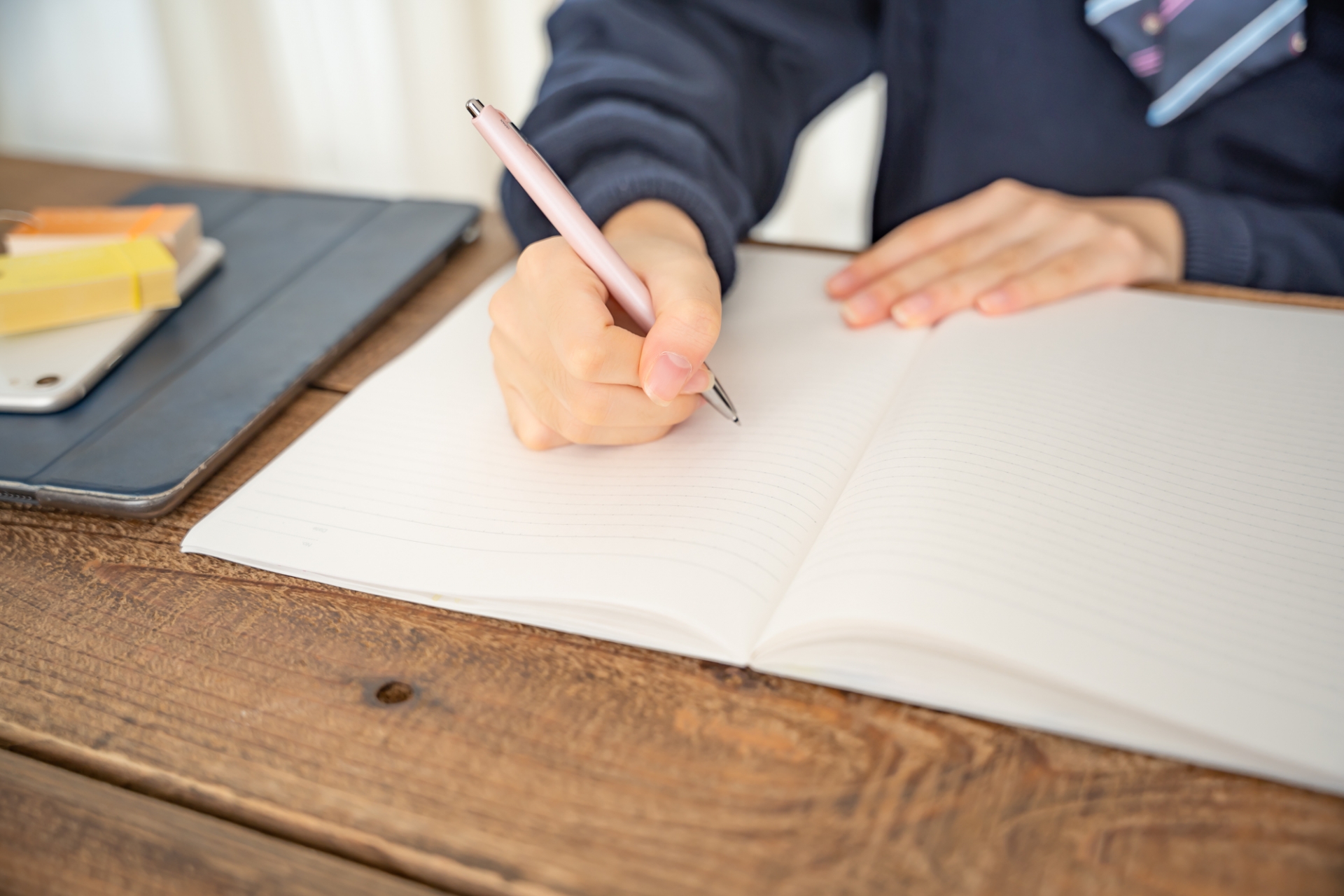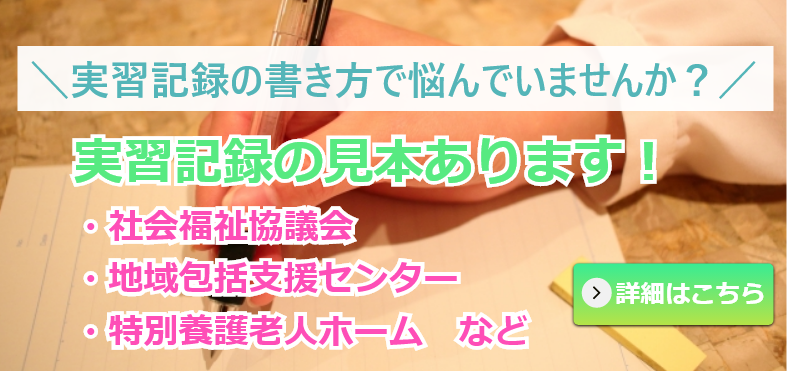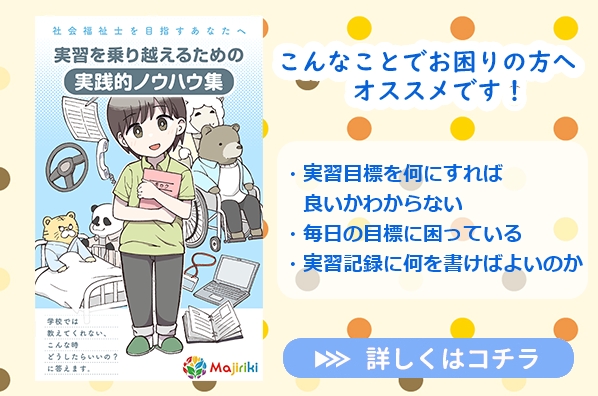この記事では、利用者中心の福祉サービスの提供を実現するために必要と考えられることについて述べる。考え方の一例として参考にしてください。
我が国における福祉サービスは、長らく行政処分である措置制度によって運用されており、行政または民間業者に福祉サービスを委託していた。費用は利用者本人または扶養義務者が所得に応じて一部を負担する応能負担であるため、収入などの所得調査が必要であり、心理的抵抗感の大きいものであった。
また、利用者がサービスを選択することはできず、行政がサービス内容や提供期間を決定するものであったため、望むサービスを受けることができないことも少なくなかった。加えて、行政が提供または民間業者に委託したサービスのであるため競争原理が働かず、サービス内容が画一的であった。このように、措置制度における福祉サービスは、あくまで行政主体であり利用者が望むサービスや費用を選択することはできなかった。
このような措置制度から社会福祉基礎構造改革によって契約制度へ転換された。契約制度は利用者本人が、その人らしい人生を営むことができるよう利用者の権利を尊重し、利用者中心のサービス提供を目指したものである。
また、福祉サービスの提供主体として民間事業者が参入したため、サービス内容の幅が広がり利用者本人が望む生活のために必要なサービスを選択することが可能となった。また、これまでは応能負担であったが使用したサービスに応じて費用を負担する応益負担に変更された。
ここでの利用者中心とは選択権が利用者にあるだけではなく、社会権的生存権、ノーマラーゼーション、自己決定などの思想や理念のもと、利用者本人の人格や生活など総合的に捉え本人の権利を尊重する考えである。
そのため、利用者の多種多様なニーズに応えるため、福祉サービスは画一的に提供されるものではなく、一人ひとりに合わせたサービス提供が行われる必要があると考える。
福祉サービスとは、介護や障害、その他の社会福祉を目的とするすべての事業のことであり、その利用者も高齢者、障害者、児童などの年齢、性別、心身状況など様々である。そのため、福祉サービスの提供に当たっては利用者の背景、生活環境、生活状況、身体的状況、心理状況などを個別に理解し、利用者の抱えるニーズを把握することが必要である。
また、福祉サービスは消費財のようにその場で使用すれば終わりという性質ではなく、サービス提供後も定期的にモニタリングを重ね、その都度利用者の状況に合わせて利用者の人生がより良いものとなるように支援していくことが求められる。
しかし、利用者の自己決定、ニーズだからと求めるものすべてを提供しようとするものではなく、時には相談員など専門職が関わることで利用者に対して助言を行い、利用者が目指す生活の実現に向けたサービスの組合わせや利用方法を決めていくものである。
そのため、サービス提供者は利用者を理解し信頼関係を構築するとともに、利用者にとって必要なサービスを利用者自身が理解し決定することができるように援助していく専門性を備えている必要がある。
また、このような福祉サービスを利用者に提供していくために、提供主体者には社会福祉倫理が求められる。一般的な民間企業であれば、コストを削減し利益を追求することが第一義的に存在している。しかし福祉サービスでは一般的な企業のようにコストを削減するために人員削減などをすることは、サービスの低下に繋がってしまう。
これは、利用者へのサービスの質の低下に直結し、利用者の生活に大きな影響を及ぼすことが想定される。福祉サービス提供主体は、福祉サービスの質の向上とともに利用者の利益を最大限に考慮していくことが重要である。
これらの方針は、サービス提供者が経営理念として明確にし、職員全体の意思統一を図ることが必要である。経営ビジョンや経営目標、事業計画を明確にすることで、職員が何を目指すべきか具体的なイメージを描くことができる。それは単なる利益目標ではなく、利用者中心のサービス提供に沿った目標設定をし、その結果を評価・検証していくことでより良いサービス提供を行うことができる。
また、組織だけでなく福祉サービス提供において現場で利用者と接する職員ひとり一人の質の向上は欠かすことはできない。社会福祉倫理を持ち、社会福祉に関する知識・技術を兼ね備え、利用者の変化に気付き、判断する能力が求められる。利用者中心の福祉サービスを実現するためには、このような職員を育てていくことも福祉サービス提供主体には重要である。
これらを総括すると、利用者中心の福祉サービスの提供を実現するためには、サービス提供者として利用者ひとり一人を個として認識し、それぞれが持つ様々なニーズに対応できるようにサービス利用に関する助言等を行い、利用者が目指すべき目標を実現できるよう支援しなければならない。また、それは利益追求をする民間企業としてではなく、社会福祉倫理を大切にしている組織ということを所属する職員に浸透させ、同じ方向を目指す職員を育てていくことで実現されるものであると考える。
参考文献
- 社会福祉士養成講座編集委員会編(2017)『新・社会福祉士養成講座11 福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版
学校では教えてくれない詳細まで記載しています!