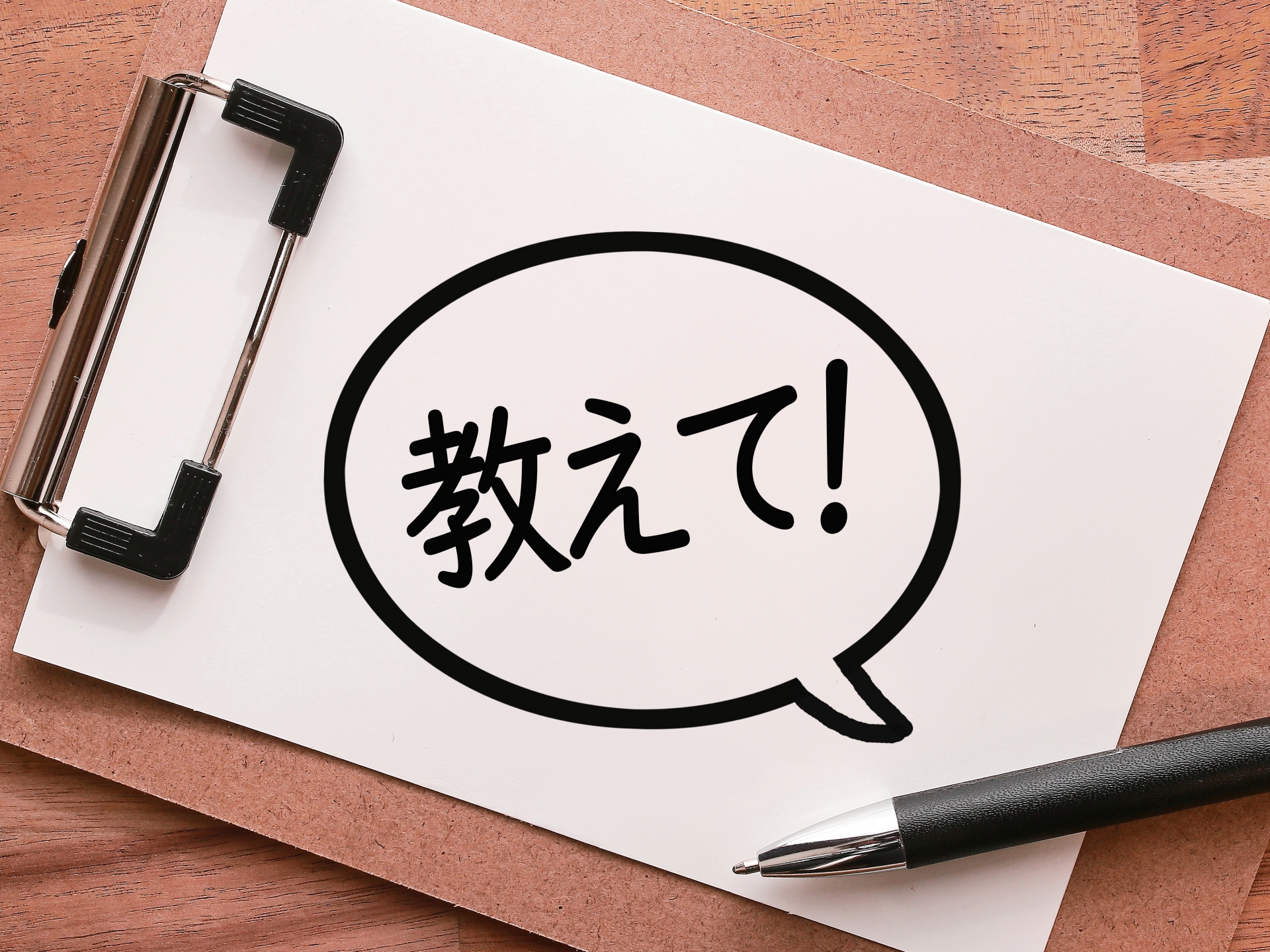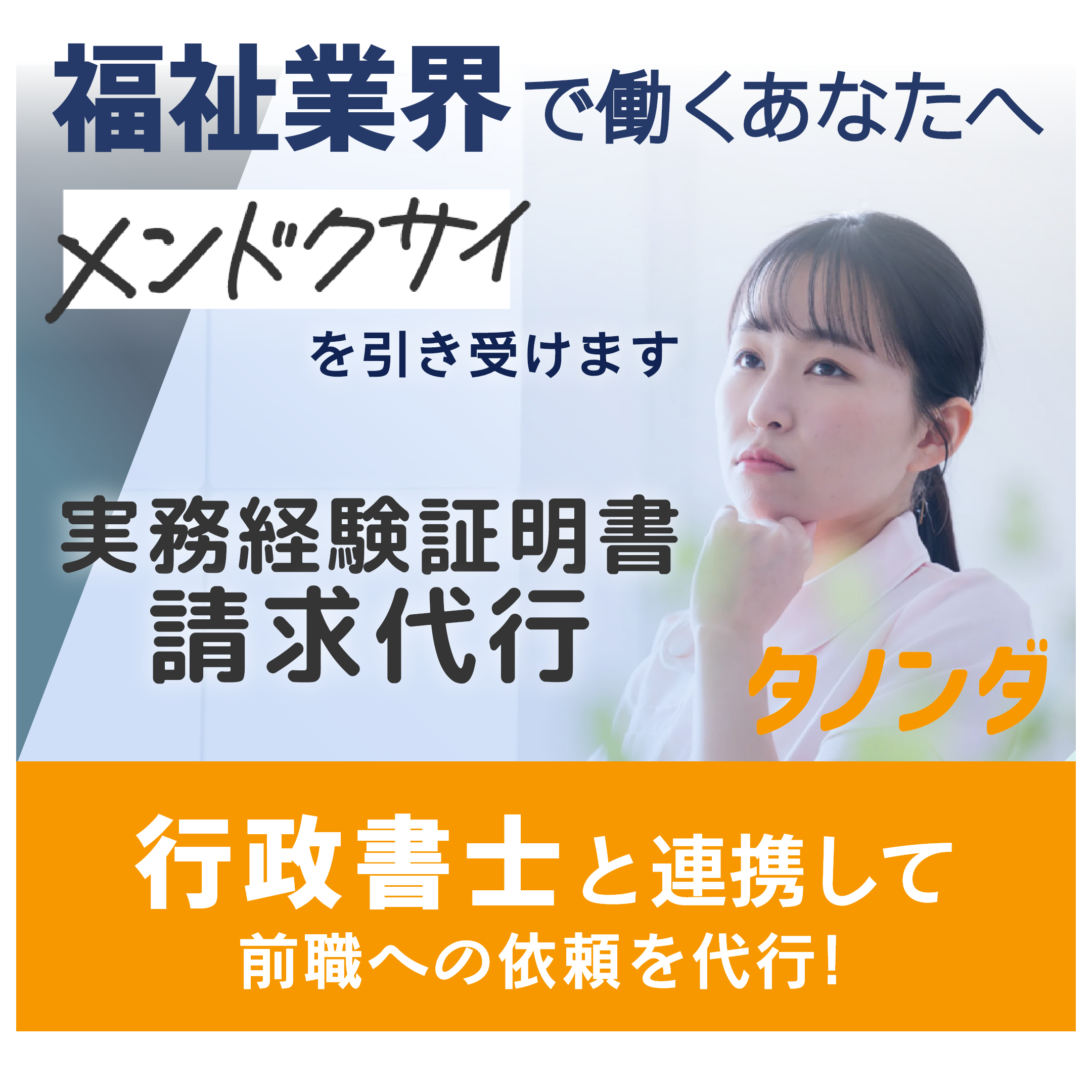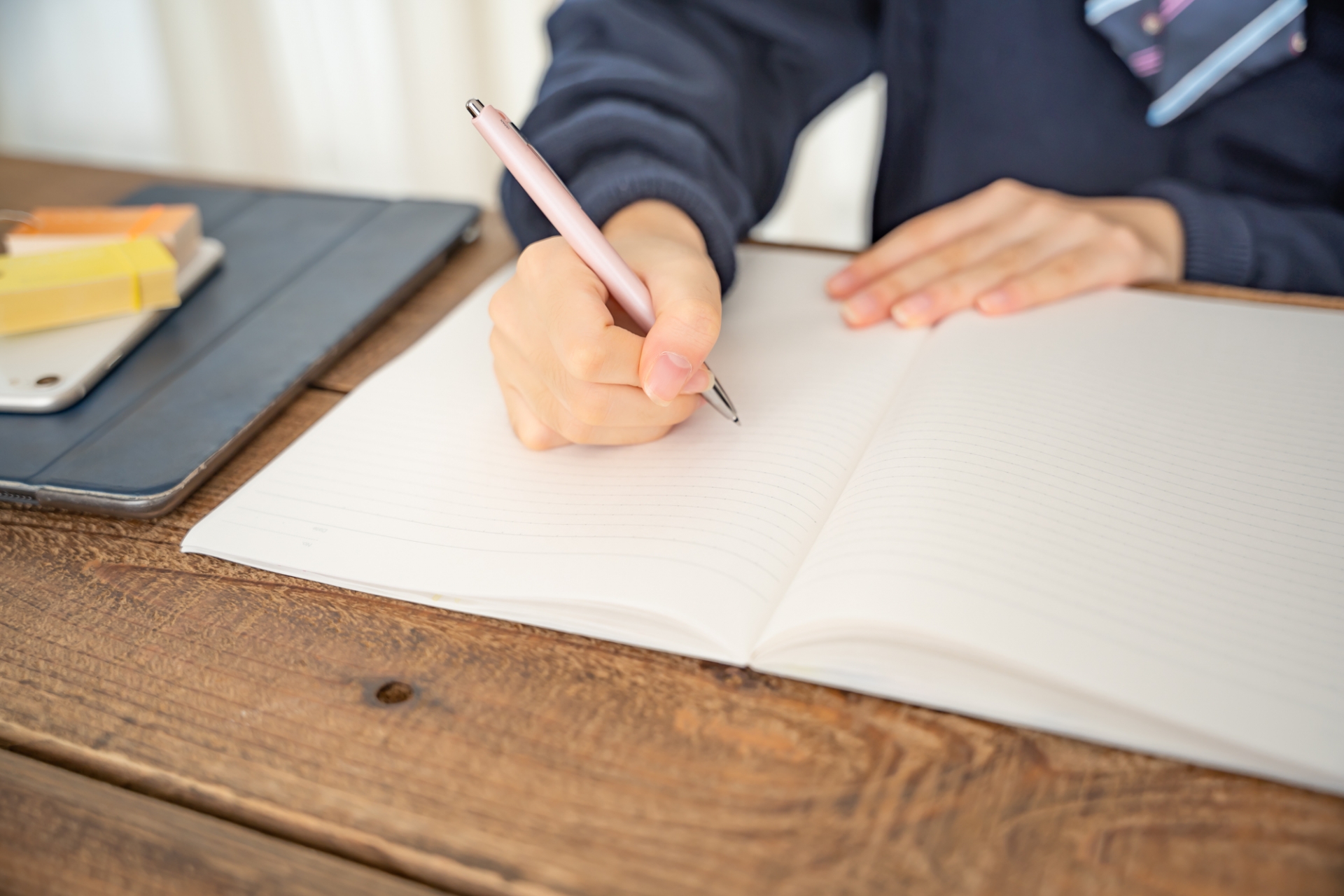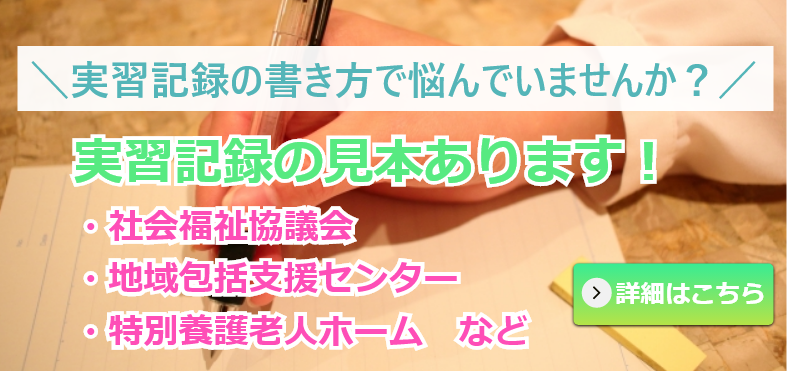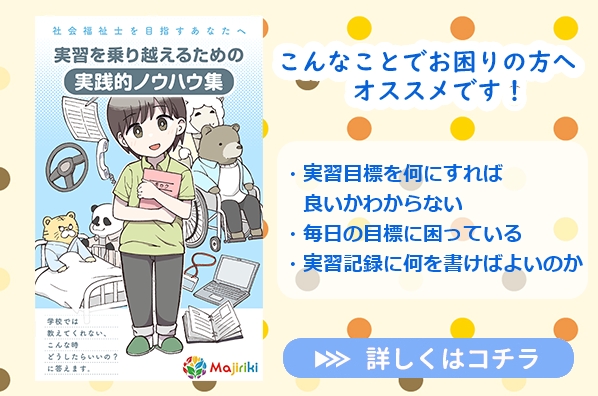この記事では、自分の権利を十分に表明する事が困難な人々に対する権利擁護システムの意義と内容について述べる。考え方の一例として参考にしてください。
権利擁護システムの意義
権利擁護の大きな転換点として社会福祉基礎構造改革が存在している。それまでの措置制度から利用者がサービス提供者と任意に契約を結ぶ契約制度へ変更されたことが主な要因である。
契約制度では、利用者が主体となってサービス提供者と契約を結ぶことになるが、自らの意思能力(判断能力)の不十分な認知症高齢者や精神障害者、知的障害者等が自ら行うことは難しい。
サービスが利用出来ないとなると、憲法25条における生存権や13条における幸福追求権が形骸化すると危惧される。そのために成年後見制度や日常生活自立支援事業等の権利擁護のシステムが存在しており、人々の権利を守る役割を担っている。
権利擁護のシステムの概要
(1)成年後見制度
成年後見制度は、判断能力の不十分な人々の生活・療養看護および財産の管理に関する事務を、本人とともに本人の支援者である成年後見人等が行い、本人の意思や自己決定を尊重しながら本人を保護するための司法制度である。成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられる。
法定後見制度は、判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族等の申し立てにより家庭裁判所が法定後見の審判を行い、成年後後見人等が選任される。その際には本人の契約締結能力に一定の制限を加えられる。選任された成年後見人が付与された代理権・取消権等の権限を適切に行使することによって、本人を保護・支援するのである。
任意後見制度は、本人が契約締結に必要な判断能力を有している間に、自己の後見のあり方を自らの意思で決めておくという自己決定の理念に沿った制度である。あらかじめ、任意後見契約を締結しておくことで、判断能力が不十分な状況になった際に、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護や支援を受けることができるのである。
(2)日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が低下した方が地域で自立した生活が送れるように支援する事業である。
具体的な支援内容としては、福祉サービスの利用開始・停止の手続きを行う、福祉サービスの利用援助や年金や福祉手当の受領に必要な手続きを援助する日常的金銭管理サービス、預貯金の通帳や実印・銀行印等を預かる書類等の預かりサービス等がある。
成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い
成年後見制度は民法等に位置付けられた制度であるが、日常生活自立支援事業は社会福祉施策としての公的サービスである。
そのため、成年後見制度では財産管理と身上監護に関する契約等の法律行為を対象として、成年後見人に付与された同意見・取消権・代理権を用いて支援を行う。対して、日常生活自立支援事業では、福祉サービスを利用するための援助や日常的金銭管理を支援の対象として、相談・助言・情報提供・調整などによる支援を行う。
参考文献
- 社会福祉士養成講座編集委員会 編(2017)『権利擁護と成年後見制度 (新・社会福祉士養成講座) 第4版』中央法規出版
学校では教えてくれない詳細まで記載しています!