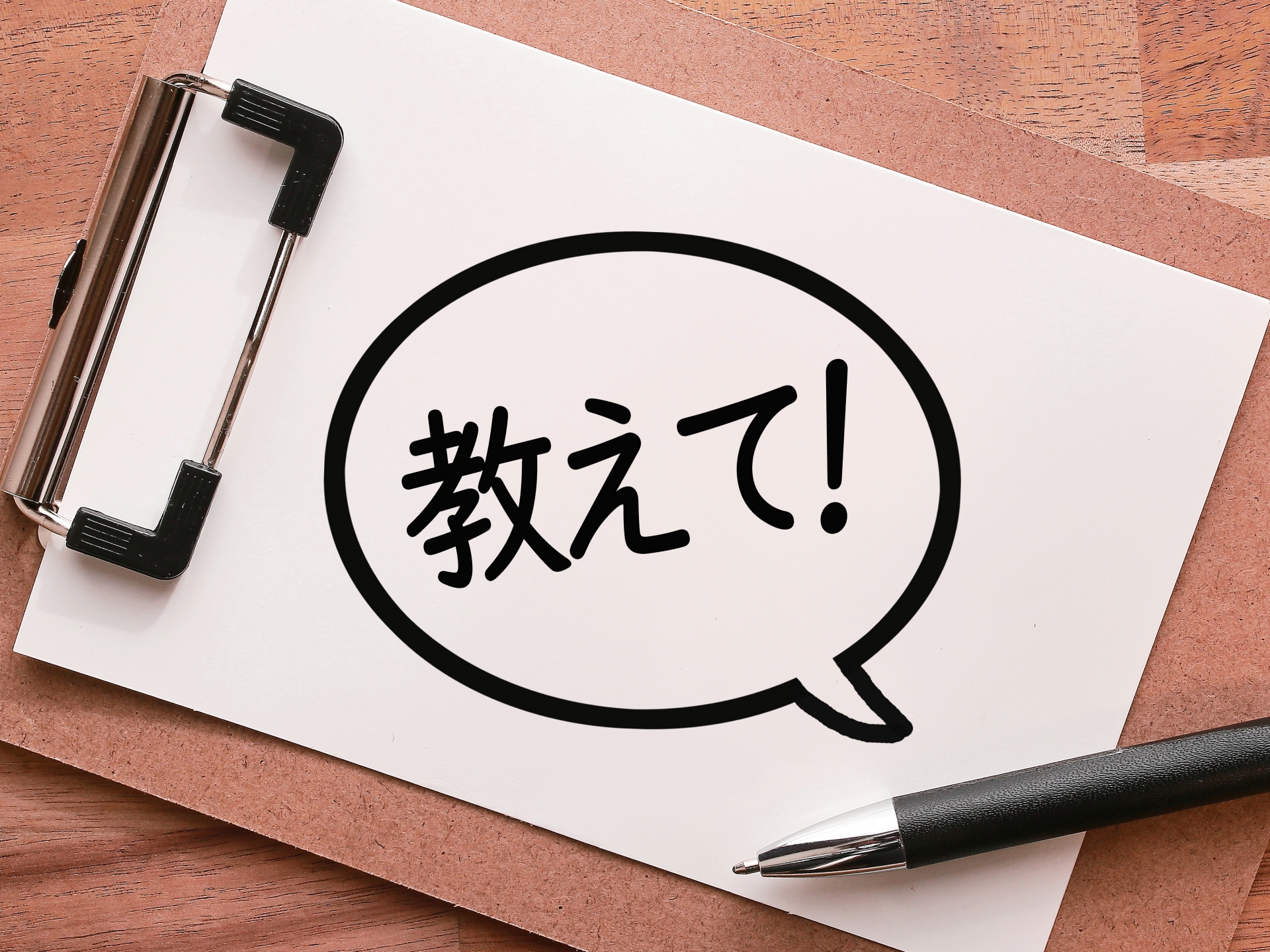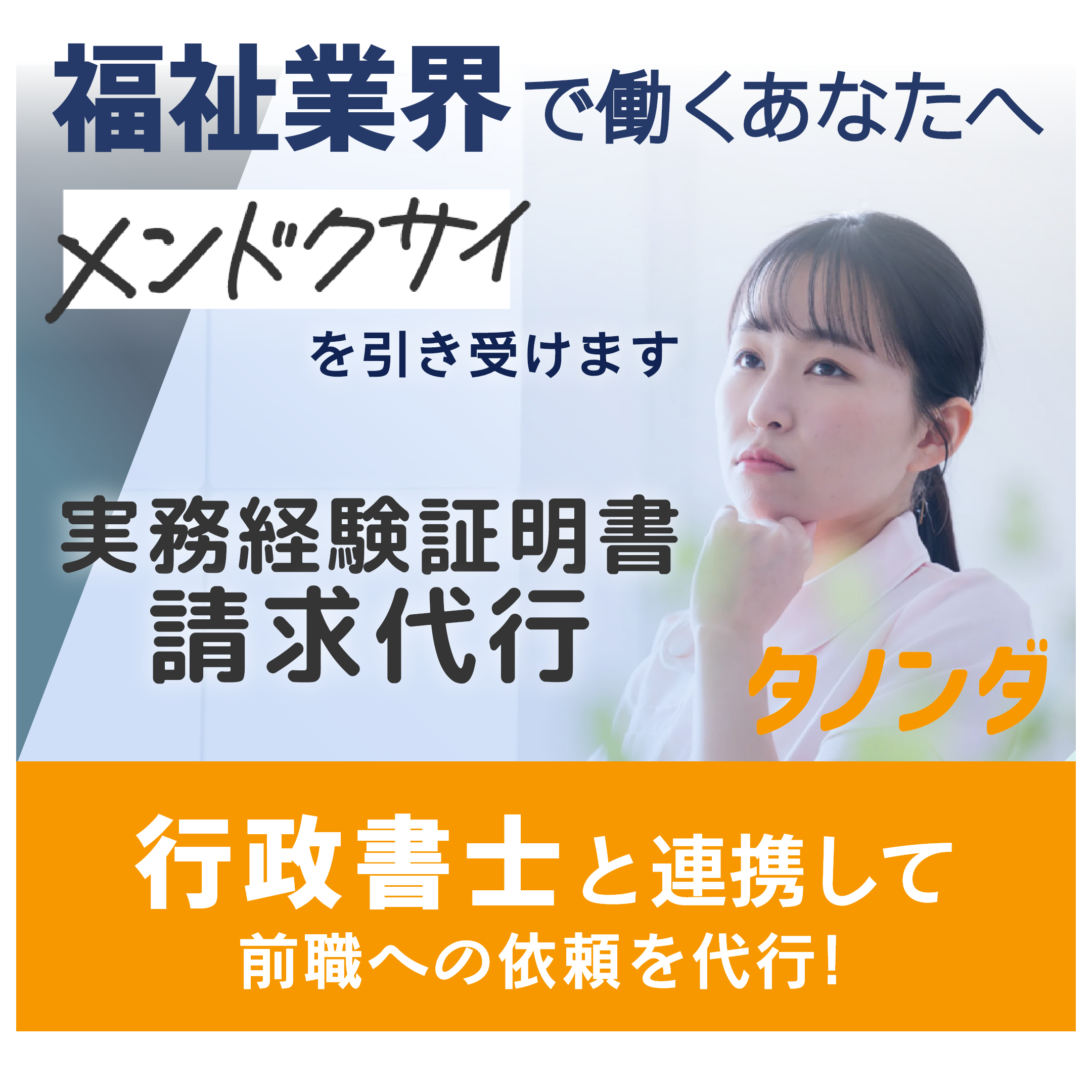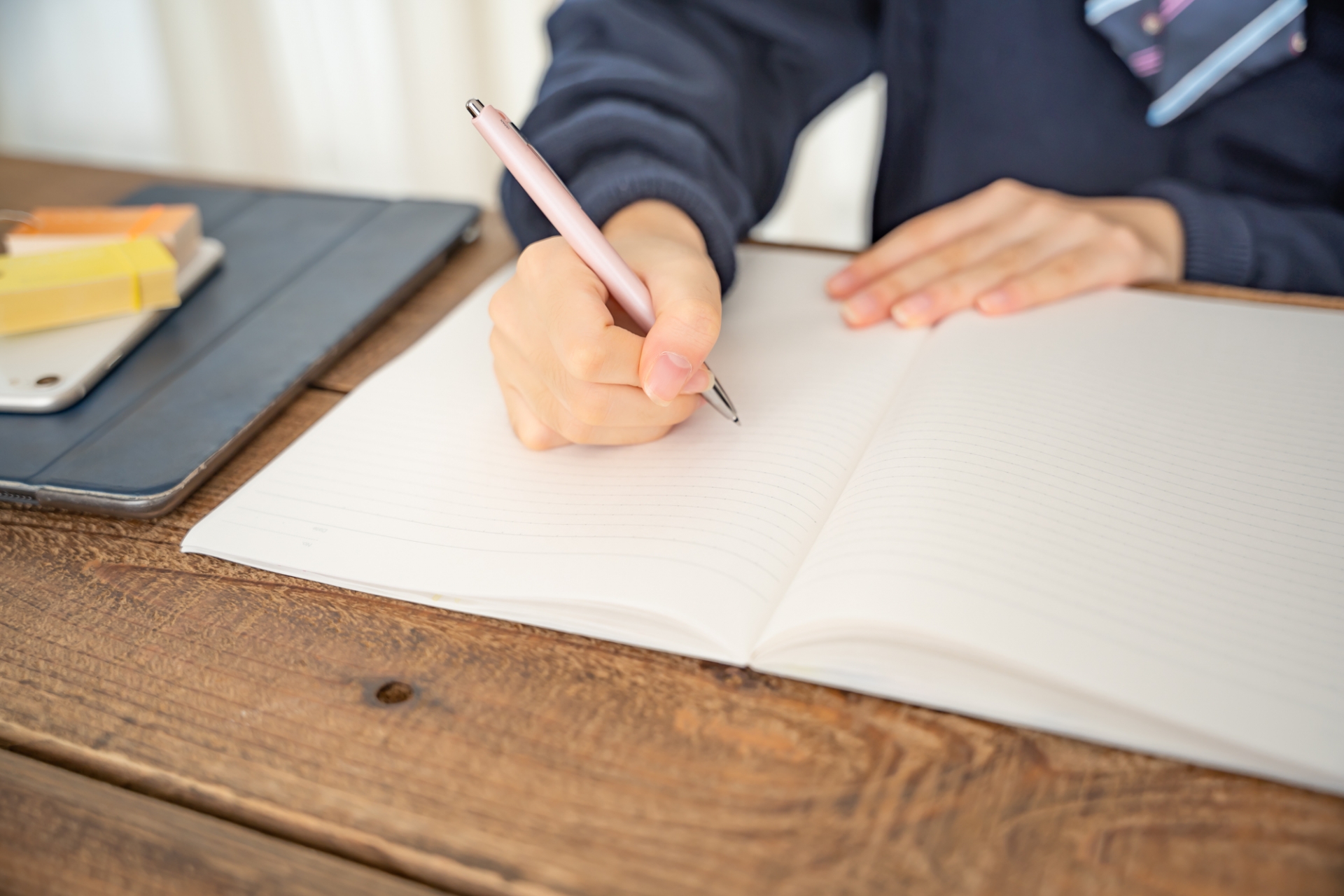社会福祉士に興味がある方に読んでもらいたい1冊です。本HPで連載していた事例を紹介しています。施設相談員がメインの事例となっており、介護福祉士と何が違うのか、どんなことをするのかよくわかると思います。小説風に書かれているので読みやすいかと思います。

1950年 (現行)生活保護法(せいかつほごほう)
社会福祉士の試験において頻出単語ですので、必ず覚えておきましょう。
まず、旧生活保護法の問題点は…
・無差別平等の原則であったが、扶養義務者が扶養をなし得る者・素行不良な者・勤労を怠る者等の欠格条項がある
・名誉職委員である民生委員を補助機関とする規定がされていた
・保護請求権、不服申立て制度がない
この制度のポイント
上記の問題を解決するために改正されました。
・日本国憲法25条に規定される生存権に基づくことが明記されました。
国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性→4原理
申請保護、基準及び程度、必要即応、世帯単位→4原則
・要保護者に権利として保護請求権を認めました。
・旧生活保護法では、5種類(生活扶助,生業扶助,助産扶助,医療扶助,葬祭扶助)であった扶助を7種類(教育扶助、住宅扶助を加える)に変更しました。
現在では、介護扶助が加わり8種類となっています。
・民生委員は、協力機関として位置づけられました。
(新)生活保護の目的は、「最低生活の保障」と「自立助長」の2つです。
なぜこの制度が出来たのか
1946年11月に日本国憲法が制定され、その第25条では、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すること、国が社会福祉などの向上および増進に努めなければならないことが明示されました。
旧生活保護法が公布されたのは新憲法の制定前であったため、憲法の趣旨を含んだ現行生活保護法が1950年に制定されました。
現行生活保護法では、無差別平等の原則に従い、制限扶助主義が撤廃され、全ての国民を対象とした一般扶助主義が確立された。扶助の基準は憲法25条に準拠し、健康文化的な水準を維持できるものとされました。
そして、保護の目的は最低生活保障と自立助長とされたことにより、保護の種類も教育・住宅扶助が追加され7種類となりました。
また、保護を受けることは権利とされ、保護請求権と不服申し立て制度が設けられました。
扶助の内容
生活保護には8つの扶助と、その他必要に応じて支給される一時扶助があり、各々に国で定められた基準により、世帯の生活に応じて扶助が支給されます。またその給付方法は、金銭が直接支給される金銭給付と、医療の給付や施設の利用、サービス提供など金銭以外の方法で給付する現物給付の2種類があります。
| 種類 | 扶助の内容 |
| 生活扶助 | 衣食その他、日常生活の需要を満たすために必要なもの、及び移送の範囲内で行われる、被保護者の飲食物費・被服費・光熱水費・家具什器費などの日常生活の基本となる部分への扶助で、原則、居宅において金銭給付が行われます。 |
| 教育扶助 | 被保護家庭の児童が義務教育を受けるのに必要な扶助で、原則金銭給付。高等学校の就学費は生業扶助に該当します。 |
| 住宅扶助 | 家賃や地代等、その補修などを必要とする時の扶助で、上限のある金銭給付です。 |
| 介護扶助 | 被保護者が要介護、または要支援と認定された場合の扶助で、施設入所などの現物給付です。 |
| 医療扶助 | けがや病気で医療を必要とする時の扶助で現物給付。投薬、処置、手術、入院等の直接給付となり、国民健康保険や後期高齢者医療制度からは脱退します。 |
| 出産扶助 | 被保護者が出産する時に行われる扶助で、金銭給付です。 |
| 生業扶助 | 生業に必要な資金、器具や資材を購入するため、または技能を習得するため等の扶助で、金銭給付。平成17年度より高等学校就学費がこの扶助により支給されます。 |
| 葬祭扶助 | 被保護者が葬儀を行う必要があるとき行われる給付で原則金銭給付です。 |
 |
|
Q&A 生活保護ケースワーク 支援の基本 (よくわかる 生活保護ガイドブック2) 新品価格 |
![]()
 |
|
[増補版]プロケースワーカー100の心得―福祉事務所・生活保護担当員の現場でしたたかに生き抜く法 新品価格 |
![]()
 |
|
新品価格 |